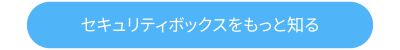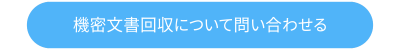【保存期間・処分方法】履歴書の廃棄で失敗しないための実務ガイド
株式会社WELL(ウェル) 営業部
採用は、会社の将来を左右する最重要テーマのひとつです。その過程で必ず扱うのが「履歴書」。
氏名・住所・連絡先・顔写真・学歴・職歴といった極めてデリケートな個人情報が詰まった書類です。
採用活動では、多くの履歴書を取り扱うことになります。
しかし、「どの履歴書をいつ、どう廃棄すべきか」明確にルール化できていない企業は少なくありません。
シュレッダー任せの運用では、処理に時間がかかる・断裁サイズが粗い・処理証跡が残らないといった問題が噴出し、現場での課題となっています。
加えて、保存義務や個人情報保護法の解釈も複雑で、理解しておかないと、法令違反や情報漏洩につながりかねません。
今回は履歴書廃棄の盲点を整理し、法令遵守と安全で効率的な仕組みが利用できる方法をご紹介し、監査やクライアントに即時提示できる“証跡”の整備ポイントも解説します。
なぜ履歴書の廃棄は“難しくて重要”なのか
履歴書は単なる紙ではありません。
氏名、住所、連絡先、顔写真、学歴や職歴、家族情報、希望条件といった、特定の個人を直接識別できる情報がすべて集約された「情報の塊」です。
そのため、一部でも外部に流出すれば、応募者本人やクライアント企業との信頼に直結します。
特に現代はSNSによる情報拡散が一瞬で広がる時代。ひとたび事故が起きれば、信用低下から取引停止、企画したイベントの中止、さらには再発防止コストといった多大なダメージを受けることになります。
さらに、監査やクライアントから照会を受けた際に「誰が・いつ・どのように処理したか」を説明できなければ、信頼性を失うことにもなりかねません。履歴書を預かった後に管理・処分を社内ルールを明文化しているかも重要です。
つまり、履歴書廃棄の難しさは「デリケートな情報」と「説明責任の重さ」にあります。
応募者から履歴書を受け取る段階で、個人情報保護の考え方を提示し、適切な取り扱いを取り決めておくことが欠かせません。
法令・社内規程の基本整理
雇用関係の重要書類は労基法109条で5年保存義務があります(労働者名簿・賃金台帳・雇入れ/解雇等に関する書類)。履歴書そのものの法定保存義務は明文ではありません。
不採用者の履歴書は目的達成後に速やかに廃棄、採用者分は台帳類等の保存対象と分け、社内規程で扱いを定める運用が一般的です。
※参考:e-Gov法令検索 労働基準法第109条
この法律に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
履歴書以外にも、会社で正社員として採用が決定すると、以下のような情報を扱うことになります。
・雇用契約書
・守秘義務契約書
・身元保証人の書類
・給与振込口座情報
・マイナンバー関連書類
こうした書類は7〜8種類に及び、いずれも厳格な管理が必要です。
履歴書も電子データでの取り扱いも増えていますが、電子運用が増える一方、最終面接段階で紙提出を求める企業も依然あります。
紙媒体での履歴書は個人情報を含むため、第三者から見られないように保管することが求められます。
事例としてはキャビネットや専用の保管箱を使用し、鍵を掛けて簡単に閲覧できなくすることです。
また、履歴書は個人情報保護法により、個人情報を適切な期間で破棄しなければならないという義務があります。保管期限を過ぎても保管し続けると、この法律に違反する可能性があり、保管している履歴書が不適切に取り扱われ、情報漏洩の原因となることがあります。
これは企業の信頼を損ない、法的なトラブルに発展しかねません。適宜処分が必要ですが、「永久保管」に近い運用をしてしまい、オフィススペースを圧迫しているケースもあります。
保管期限が過ぎた履歴書は適切に処分することが、法的な問題を避けるだけでなく、経済的な観点からも推奨されます。
不採用者の履歴書
選考が終了した時点で、履歴書は「利用目的を終えた個人情報」となります。そのため速やかな廃棄が必要です。
不採用者の履歴書について法律による返却義務や保管義務はありません。しかし、すぐに処分も心配な場合があるので、社内で保管期間を定めておき、その保管期間が過ぎたら廃棄する方法で管理している会社が多いでしょう。
あらかじめ保管期間を管理する部署に周知しておくとトラブルを避けることができます。
実務的にはクレーム対応や再選考の可能性を踏まえ、3〜6ケ月程度で廃棄するのが一般的であり、社内規程に明記しておくことが望まれます。
採用に至った場合
採用が決まった応募者の履歴書原本については、不採用者とは扱いが異なります。
雇用関係書類と一緒に扱うのではなく、別管理とする方が無難です。
採用後は、労働基準法に基づく雇用関係書類の一部として保存義務があり、賃金台帳や労働者名簿などの労働関係書類を5年間保存することが義務付けられています。
履歴書は法定保存文書に明記されているわけではありませんが、労働者名簿や雇用契約書と密接に関連する性質を持つため、同様に5年間の保存運用を行うことが望ましいとされています。
税務関係書類(源泉所得税等)では7年保存が求められる場合もあり、それぞれルールが異なるので、会社でルールを決めて管理する必要があります。
※制度改正や経過措置により保存期間の扱いが変動する場合があります。最終的な判断は必ず社会保険労務士など専門家に確認してください。
シュレッダーで履歴書を廃棄するのは心もとない
履歴書もシュレッダーにかけて処分をすればいいと思っていませんか?実はここに大きな落とし穴があります。
・シュレッダーした履歴書を一般ごみに混ぜて廃棄
→もともと機密情報なので、重大なリスクになる
・アルバイトや派遣スタッフに履歴書のシュレッダー処理を任せる
→ 誰が処理したか追跡できない人に処理させるのはNG
・小型シュレッダーで履歴書の大量処理
→ 詰まり・断裁サイズが粗い・処理証跡が残らない
・複数の担当者が履歴書のコピーを持ち出し
→ 原本は厳格に管理されても、コピーが放置される
極端な例も入れてありますが、履歴書を1枚ずつ投入し、細断するのに膨大な時間を要します。
オフィス用の小型機では、「完全抹消」とは言えないため、情報漏洩のリスクは残ります。
ピーク時にはシュレッダー渋滞や紙詰まり、故障が頻発し、処理が遅延することも考えられます。
履歴書は機密情報であるため、シュレッダーでは「誰が・いつ・何を処理したか」を記録できません。監査やクライアントに「処理の証跡を示してください」と求められても、証明できないのも困ります。
履歴書の廃棄は「処理の仕方」が問われるのです。
履歴書の処分は常にではない
履歴書は、会社の活動期間の中でも日常的に発生する書類ではありません。学生の就職活動が活発な時期に履歴書の取り扱いが集中して発生します。
そのときにまとめて保管するなどの対処を行いますが、履歴書の処理に関する法律は、主に労働基準法と個人情報保護法が関わってくるので、その場ですぐに処理をすることは難しいでしょう。
保管期限が満期になったときにまとめて処分をすることが多い書類になります。
また、オフィス移転や拠点統合時に保管についての見直しを行う場合も大量に書類を処分をする必要が出てくることがあるでしょう。
箱回収で一気に処分が適切「分別ゼロ × 証跡アリ」
そこで有効なのが、段ボール回収の活用です。履歴書だけでなく、人の目に触れないように処分しなければいけない書類が多いのであれば、WELLの機密書類回収サービスがおすすめです。
会社で処分したい機密書類をまとめて段ボールに入れて密封してもらったものをそのまま回収します。ホチキス・クリップ・バインダーごと投入しても大丈夫です。
回収証明書や処理証明書の発行を行いますので、 監査やクライアント対応に強いです。
「どのように廃棄したか」を証跡で示せることが、ガバナンス上も大きな安心につながります。
また、現場の実感として「捨て方を考える時間」がゼロになるのも大きなメリットです。
情報漏洩の事故を防ぐ確率が大きく高まります。
日々、機密書類が発生する場合は、社内にセキュリティボックスの設置も可能です。
南京錠付きのボックスになりますので、安全に回収・破砕し、処理証明書も発行されます。
CSRや環境対応の説明の根拠にもなります。コスト面でも、社員が何時間も作業する人件費を考えれば、外部委託で機密書類の箱を回収のほうが合理的といえるケースが多いです。
まとめ
履歴書の廃棄は「安全・速い・証跡あり」を同時に満たせるかどうかが勝負です。
現場が迷わない常設の仕組みを導入することで、シュレッダー行列も、机上の放置も、説明責任の不安も一気に解消できます。
登録会やオフィス移転など、大量発生のピークが来る前に、セキュリティボックスの導入を検討してみてください。履歴書を含むすべての応募者情報は「個人情報」です。
社内で仕組みを整え、情報の漏洩を会社全体で遵守することが大切です。
株式会社WELL(ウェル) 営業部
ビジネスの中で廃棄される機密書類や、不要になった古紙などを、迅速な回収、安全な再資源化を行なう機密書類処理のリーディングカンパニーの営業部です。